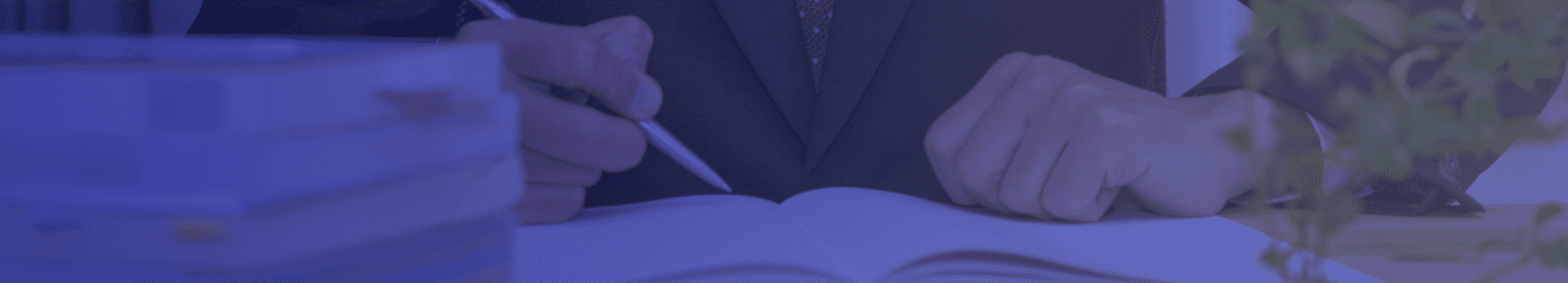
弁護士コラム
第127回
『奨学金の返済期間中の看護師でも退職代行を利用できる理由』について
公開日:2025年6月9日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
第127回『奨学金の返済期間中の看護師でも退職代行を利用できる理由』についてコラムにします。
退職代行と奨学金の分割交渉の依頼や奨学金を借りている看護師の方が退職代行をご希望される場合には、弁護士の退職代行からお申し込みください。

目次
1.看護師の奨学金が有効になるケースはほとんどになります。
看護師の方が資格取得時に、勤務先病院から奨学金を支給されているケースはとても多いです。
中には、資格取得時の専門学校で、専門学校側で勤務先病院をあっせんするケースもあります。また、その病院に勤務するまでに、学費や生活費を含めて100万円から500万円程度の奨学金の支給を受けている場合がほとんどです。
実は、この奨学金については、裁判上、退職時に返済することに関しては、『返済』するということについて争いはありません。
※勤務先病院が退職者に対して、返済請求できるか否かについては、コラム第28回をご参照ください。
参考裁判例
看護学校の学費等について6年間で設定していた事案で、金銭消費貸借契約の形を取ったとしても、実質的に労働基準法第16条の損害賠償の予定に該当する場合は法違反になるとの判断があります。この事案では、労働基準法第14条の有期契約について3年を超える期間を定めてはいけないというところに着目し6年はその倍であるとこと、勤続年数に応じた減額措置がないこと、返済額が基本給の約10倍の高額であることなどを指摘して無効と判断しています(広島高裁平成29年9月26日)。
最近の看護師の奨学金のケースでは、❶6年以内の5年以内の勤務を条件としていること、❷1ヶ月勤務毎に、月の免除額(償却額)が定められていること、制度設計自体が裁判例を十二分に意識したものになっています。
2.奨学金の返済と退職代行について
ここまでをまとめますと、退職時に、奨学金の返済を一括にするケースが有効となると、退職時に、一括で支払いができないケースはどのようにすべきでしょうか?
ここからが今回のコラムの本題になります。
前提として、退職時に、残った奨学金について一括で返済できる看護師の方は、退職したいと思った場合には、退職代行を依頼することは問題ありません。退職と奨学金の返済とは、別問題にあたりますので、退職できます。
ごく稀に、奨学金を返済しなければならない場合には、退職できますか?というご質問をいただきますが、スムーズに退職できますので、心配がない旨について私から回答しています。
話を元に戻しまして、奨学金を一括で返済できない場合には、退職代行と一緒に『奨学金の分割交渉』を行うことがあります。
職場の病院が分割交渉に合意するか否かについては、病院側の意向があります。
分割交渉の際に、分割の合意をするかどうかは、病院次第になります。
しかしながら、諸般の事情によっては、分割の合意に行うこともあります。
一般的には、①退職時に奨学金をいくら返済するか、②全額の一括返済ができないとしても、まとまった額の返済ができるか、③毎月の返済額、④退職理由、⑤退職者本人や保証人の資産の有無、⑥公正証書の作成の有無、など諸般の条件を総合的に勘案して、交渉することになります。
3.まとめ
奨学金の分割交渉をした際の注意点としては、連帯保証人が居る場合には、その連帯保証人に直接、連絡や奨学金の請求が行くケースもありますので、注意しないなりません。
退職するにあたっては、慣れない職場環境や、パワハラを受けていて退職者自身がとても退職を悩まれている相談を受けるケースもあります。職場の病院自体も、看護師の絶対的な人数確保のために、苦肉の策として、奨学金の導入をとっているため、問題はかなり根深いものと言えます。
奨学金の分割で悩まれる場合には、遠慮なく私までご相談ください。力になります。
・関連コラム
第123回『看護師のための退職代行時の奨学金(借入金)と分割交渉』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る