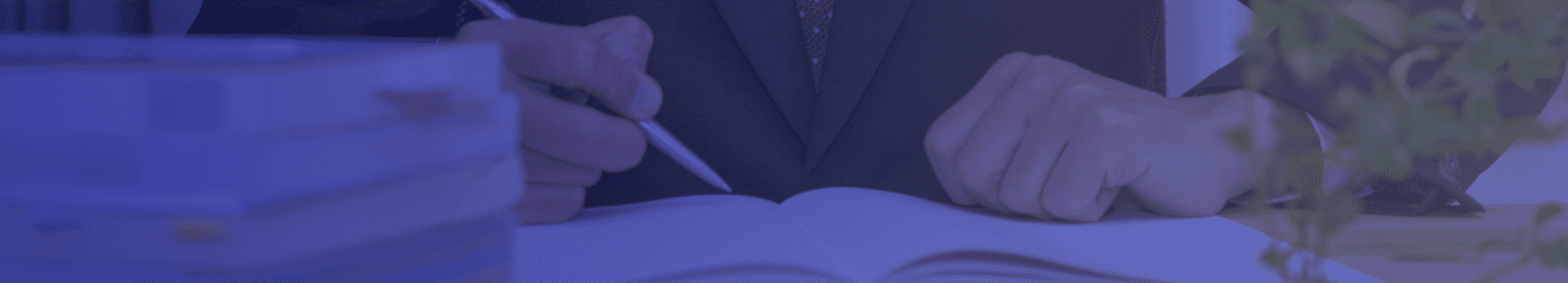
弁護士コラム
第130回
『国土交通省の退職代行は弁護士がおすすめな理由』について
公開日:2025年6月27日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第130回は『国土交通省の退職代行は弁護士がおすすめな理由』についてコラムにします。
国土交通省の退職代行については、弁護士法人川越みずほ法律会計の退職代行はこちらのサイトからお申し込みください

目次
1.弁護士による国土交通省の退職代行がおすすめな理由
最近では、比較的、入職から退職までの期間が短い国土交通省にお勤めの方からの退職代行のご相談が増えています。
退職代行のご相談時に精神的に限界なケースでは、退職代行ではなく、病気休暇の代行に切り替えて受任するケースも増えています。
今回は、国土交通省にお勤めの方の退職代行について解説していきます。
国土交通省の職員の方は全体で約6万人となっており、他の省庁の職員の方より多くなっています。
また、依頼時の特徴としては、出向しているケースも多くどのように退職代行を依頼し、どのように退職代行を進めるかについてよくご質問を受けます。
まず、出向していた場合でも、退職代行の流れは変わりません。基本的には、出向先に、退職代行の退職通知(受任通知書)を送ることがほとんどです。
受任通知書については、出向先(職場)に対して、FAX、メール、電話連絡を行います。弁護士が連絡を行いますので、受任通知した段階から『出勤することはなく、職場との連絡は不要』です。
弁護士が行う退職代行というサービス自体は退職を代行するだけではなく、退職手続きを代理するサービスです。したがって、退職代行サービスにあたっては、代休や年次休暇があれば、その代休や年次休暇を消化して退職することができます。
細かい点を言えば、私物があれば、その私物を着払いで送る交渉も含まれます。最近では、某退職代行会社と弁護士の違いを教えて欲しいと言われますが、退職代行会社は、退職に関して、交渉することはできません。
国土交通省の職員は、国家公務員であるため、国土交通省から退職について承認が必要であるため、その承認の過程で、退職について交渉が必要となります。
交渉が必要な場合には、退職代行会社が退職代行をした場合には、弁護士法72条違反の非弁行為にあたり違法無効な退職代行になります。したがって、国土交通省の職員が退職代行を依頼するのは弁護士にすることを強くおすすめします。
仮に、弁護士法72条違反の場合には、年次休暇消化もできないことになるため、懲戒免職になる可能性もありますので、退職代行会社に依頼するのはやめた方が良いです。
その点、弁護士であれば、退職代行(退職代理)の制限はありませんので、正式な退職代行手続きを踏めば懲戒免職になることはなく、自分で退職手続きをしたケースと同じ扱いである自己都合退職になります。
お困りでしたら、弁護士法人川越みずほ法律会計までご相談ください。力になります。
2.まとめ
国土交通省にお勤めの方から話を聞く際に、職場に馴染めないや、業務が過重である旨の相談を受けます。上司からの当たりも強いなど、今後、長く勤務してもらうためにも、国土交通省としても取れる方策をすべきだと思っています。
国土交通省にお勤めの方で退職を希望される方は、遠慮なく私までご相談ください。力になります。
また、体調不良などで、退職という重大な結論を一旦保留して退職ではなく病気休暇を取得してしばらくお休みをするという方法もありますので、体調不良がある方は私までご相談ください。
国家公務員の病気休暇については、コラム第118回『公務員(国家公務員、地方公務員)の方や民間企業にお勤めの方には休職代行(病気休暇取得代行)がおすすめな理由』について、をご参照ください。
・参考コラム
第107回『国家公務員の退職代行がおすすめな理由』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る