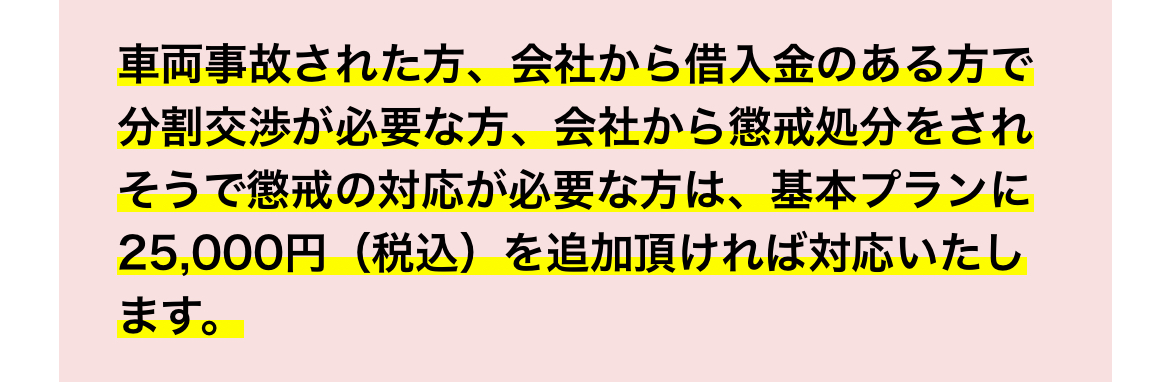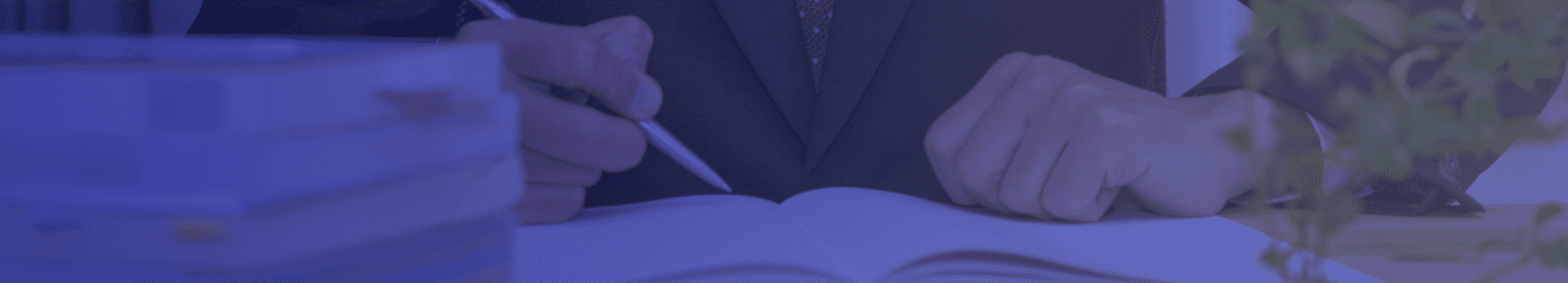
弁護士コラム
第173回
『退職代行サービスの支払いが後払い可能な場合』について
公開日:2025年10月7日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第173回は『退職代行サービスの支払いが後払い可能な場合』についてコラムにします。
後払いで退職代行サービスをご依頼したい場合には、弁護士の退職代行のページからお問い合わせください。
退職代行サービスの認知度が高まるに連れて依頼する側のニーズも多様なものになっています。その中のニーズの一つとして、『後払い制度』がその退職代行サービスを行う弁護士事務所にあるかについては十分調べらることをおすすめしています。
実は、世の中のサービスのかなりの割合が後払いになっています。特に慣習的に企業間サービスの場合には後払いが通常になっています。
私は、そのサービスが今後、慣習的なものになっていくのであれば、支払いについても後払い制度を広く採用すべきだと思っています。

目次
1.後払いサービスのメリット・デメリットについて
退職代行サービスを利用する側にとっての後払いのメリットは、
①費用調達ができなくとも即日のタイミングで依頼することができる。
②給与支給時のタイミングで支払いする予定が立てられる。
③退職代行サービスについて不安がある際に、その退職代行サービスの質などが支払いする前にチェックすることができる。
退職代行サービスを行う側のメリットは、
❶後払いで退職代行を受けることができるかについて事前に審査することができる。
❷給与支給時に合わせて退職代行サービスの委託費用をもらうこともできる。
では、双方のデメリットを挙げます。
退職代行サービスを利用する側のデメリットは、あまり思い浮かぶものがありません。
次に、退職代行サービスを行う側のデメリットは、支払いの不安があるという点が大きいです。一般的に、企業間の取引の場合には、与信管理という言葉があります。
後払いサービスを選択しても、その支払いがしっかりと行われるかという管理が事前に行われます。退職代行サービスの後払いで受託を受けるかは、この与信管理も大事な一つになります。
したがって、私の方で後払いで退職代行サービスを行うにあっては、いくつかヒアリングを行うことがあります。仮に、後払いで退職代行サービスを依頼できない場合でも、私の方では2分割で退職代行を行うことが一般的です。
2分割の支払いのタイミングは、『依頼時に半額払い、依頼から1ヶ月経過日までに半額払い』となります。
クレジットカード(カード決済)で2回払いでも受けることができます。
2.会社から借入金があるパターンについて
会社からの借入金のある方の場合には、2分割で退職代行サービスを受けることが多くあります。
※後払い一括支払いの場合もあります。
簡単に説明します。
私の行う退職代行サービスに借入金の分割交渉プランを付けていただく場合には、総額の支払いが47,000円になるとします。その際、依頼者としては、諸事情で47,000円を一括で事前に支払うことが難しい場合もあります。その際、2分割払いとして、23,500円×2回を選択する方もいらっしゃいます。
また、業務委託の退職代行サービスを申し込みつつ借入金の分割交渉についても依頼する場合には、総額の支払いが58,000円とします。その際、27,500×2回を選択される方もいらっしゃいます。
3.まとめ
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る