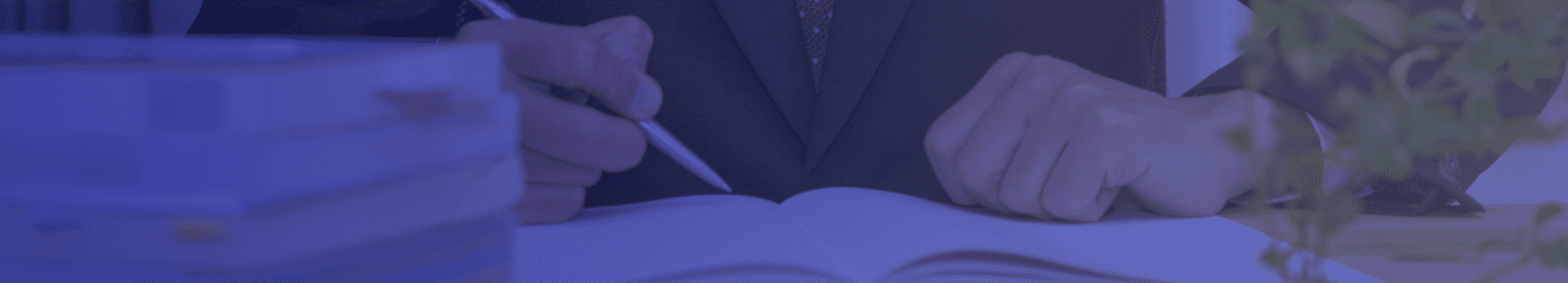
弁護士コラム
第176回
『役員のための退職代行は弁護士がおすすめな理由』について
公開日:2025年10月10日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第176回は『役員のための退職代行は弁護士がおすすめな理由』についてコラムにします。
役員の退任代行についてのご相談は弁護士の退職代行からお問い合わせ下さい。

目次
1.役員の退任代行について
役員という用語は、社内的な用語で使う時と、「社長、頭取、副社長、会長、専務、常務、執行役員」まで含まれる広い用語になります。
今回は、退任に関するコラムですので、社内用語の役員ではなく、会社法上の「役員」の退職(退任)代行について弁護士の清水隆久が解説します。
会社法上の役員については、会社法第329条(選任)に規定されています。役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。
以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。取締役、会計参与、監査役(役員)になるにあたっては、会社と役員との間で、委任契約を結んでいます。
会社法第330条
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
委任に関する規定は民法に定められていて、委任契約の解除については、解除通知をしたその日が解除日となる即日解除になります。
民法第651条第1項
委任は、各当事者がいつでも解除をすることができる。
法律上は、「役員」の方が退職したいと言えば、すぐに退職できるため、ご自身で退職の手続きができないようでしたら、遠慮なく私までご相談ください。役員の退任代行をお受けできます。
2.役員の退任にあたっての諸問題
①役員の退任代行時に会社が退任手続きをしてくれない場合
②役員の方が連帯保証人になっている場合
③株を持っている場合
④損害賠償対応が必要な場合
①役員の退任時に会社が退任手続きをしてくれない場合には、抹消登記について、裁判手続きをとる必要があります。
退任登記の手続きをする訴訟としては、『役員退任登記手続請求訴訟』を提起することが出来ます。もっとも、取締役会設置会社等において辞任により取締役の最低人数に欠員が生じる場合には、新たな取締役が選任され就任するまでの間、辞任した取締役は引き続き取締役としての権利義務を有することが規定されています。
この場合には、辞任届を出しただけでは退任登記手続請求が認められませんので、裁判所に対し、退任登記手続請求と併せて仮取締役の選任の申立てを行う必要があります。
※代表取締役の退任登記手続請求については、取締役設置会社に関わらず仮取締役の選任の申立てを行う必要があります。
②役員の方が連帯保証人になっている場合
役員の方が社宅や銀行借入やリース車両の連帯保証人になっているケースが多くあります。
私が役員の退任代行をするにあたっては、その保証人の交代の交渉をするケースが多くあります。
③会社の株を持っている場合
株式を保有している場合には、退任代行にあたって、株式の買取請求を会社にすることもあります。
非公開会社の場合には、第三者に対して株式譲渡の承認を会社に求めて、会社の承認がなく第三者に譲渡した場合に対しては、会社に譲渡の効力を主張できません。したがって、譲渡の承認や譲渡の調整をするケースが多くあります。
※譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること(会社法第107条第1号)
④損害賠償対応が必要な場合
役員の退任にあたっては即日退任が認められている一方で、損害賠償が発生するかどうかについても検討しなければなりません。
即日退任の場合には、⑴『不利な時期』に解除した場合に、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、⑵やむを得ない事由があったときは、この限りでない、と民法第651条に規定されています。
この点、⑴不利な時期とは、委任の趣旨はあくまでも当事者間の信頼関係を前提として、成立する契約であるため、❶委任者がその委任事務を自ら処理したり他人に処理させたりすることができないような時期、を言うものと考えます。
次に、⑵やむを得ない事由とは、委任の趣旨はあくまでも当事者間の信頼関係を前提としていますので、その信頼関係を没却しても、例外的な場合をいうと考えます。具体的には、❷生命、身体などに、重大な影響を与える事由を言うと考えます。
すなわち、民法第628条第1項のやむを得ない事由よりも加重された理由が必要と私は考えています。例えば、健康上の理由を辞任、退任理由とする場合には、それ相応の健康上の理由が必要と考えます。
3.まとめ
役員の退職代行については弁護士による退職代行サービスを利用する必要があります。民間の退職代行サービスや労働組合の退職代行サービスでは対応できないためです。
民間の退職代行サービスは、非弁のおそれがありますし、役員の加入を認めた労働組合は、組合の法適合性を欠くため労働組合の成立自体を否定することになるからです。
役員の退職代行または退任代行でお困りでしたら、私までご相談ください。力になります。
※労働組合法第2条第1号
役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
・参考コラム
第23回『取締役の退職代行(辞任代行)』について
第111回『代表取締役の退職代行(退任代行)がおすすめな理由』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る