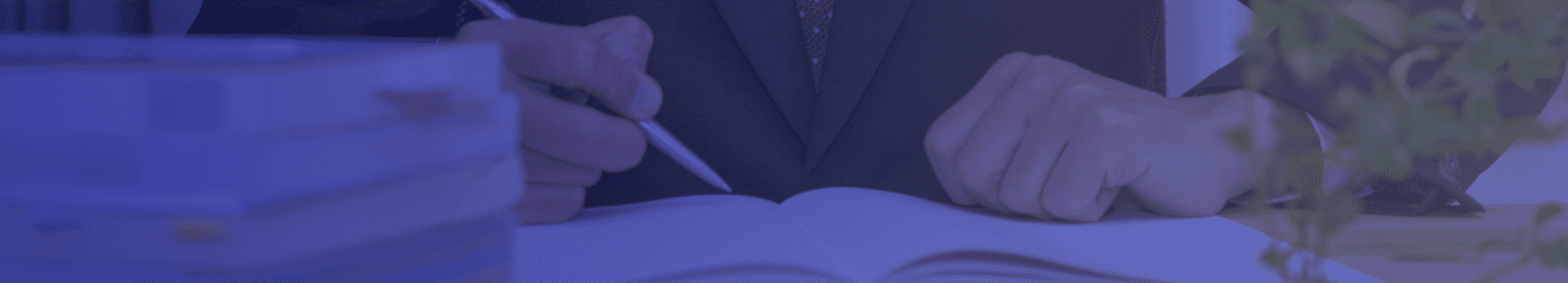
弁護士コラム
第133回
『公務員による退職代行のリアルな体験談と相談窓口(川越みずほ法律会計)』について
公開日:2025年7月2日
退職
弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の清水隆久と申します。
退職代行を専門的にはじめて早いもので、数年が経ちました。
その間、数多くの退職代行をした経験から「これは」と思うことをコラムにします。
コラム第133回は『公務員による退職代行のリアルな体験談と相談窓口(川越みずほ法律会計)』についてコラムにします。
公務員の退職代行については、弁護士法人川越みずほ法律会計の弁護士の退職代行からお問い合せください。
今回は、税務署に勤務されている職員の方からのご相談内容(退職代行)についてご紹介させていただきます。
今回は、税務署職員の退職代行についてご紹介させていただきますが、今回のコラムはほとんどの公務員の退職代行に当てはまります。

目次
1.公務員(税務署職員)による退職代行について
税務署に勤務して7年程度になります。仕事のやりがいがありますが、ハードワークのため、精神的に体調を崩してしまいました。また、転勤の辞令を受けていまして、良い機会だと思い、退職することに決めました。
年次休暇消化するにあたっては、弁護士に依頼することで確実に消化できると思いましたし、退職手続きをするのは、転勤先であったことから、自分で話をするのが面倒だと思い、退職代行を依頼することにしました。
結果的に、年次消化もでき、退職手続きもスムーズでしたので、依頼して良かったと思います。
今回の公務員による退職代行について、弁護士の清水隆久が解説していきます。
税務署職員(国税庁)の方の退職代行の特徴は、一般行政職の公務員による退職代行とあまり違いはありません。しかしながら、電話が繋がるのが8時半以降であるのと、各税務署には、ファックス(FAX)がないことが他の公務員と異なります。
実は、所属の税務署に本来的には8時半までに出勤しないとならないので、8時半までに所属の税務署に『出勤しない旨の連絡』をしないとならないのですが、税務署に電話連絡ができるのが、8時半以降のため、8時半から8時45分の間に電話連絡することになります。
さらに、各税務署は、外部からのファックス(FAX)を受信することはできないため、受任通知書をファックスするためには、各国税庁に受任通知書をファックス(FAX)して、内部的に回してもらうようにします。
数年前には、退職代行時の辞令交付については、直接受け取るように各税務署から要求されていましたが、今では、辞令交付を含めて、必要な作業は全て郵送で行っていますので、直接、出向くことはありません。
ここまでをまとめますと、税務署職員の退職代行を弁護士に依頼した際には、年次休暇の消化から退職手続きまで全て代理で出来ますので、依頼者が職場と連絡を取る必要はありません。
もっとも、公務員に共通して言えることですが、退職願の作成は、依頼者自身で行ってもうようになりますので、公務員の退職代行の際には、所定の退職願を私の方で取り寄せ、退職願の記入をして貰います。
※辞職願及びその撤回は、身分の得喪に関わる公法上の意思表示であるため、自ら直接行うことを要し、使者を介することは許されるが、代理人による意思表示は許されないとされいます(昭和39年6月22日 奈良地裁)。
2.まとめ
各税務署職員の退職代行では、最低でも20日程度の年次休暇を保有していることが一般的ですので、その年次休暇消化をした段階で退職になることが一般的です。
しかしながら、体調不良などにより年次休暇を全て消化した場合には、退職代行したその日を退職日とする即日退職の交渉をすることが多いです。
各税務署の職員の退職に関する規定(何日前に退職の意思を伝えるなどの規定)は特にないため、逆に言えば、即日退職も認められることになります。
さらに、各公務員のコラムでもご紹介している内容ですが、体調不良の場合には、退職の前に病気休暇(90日)を取得することをおすすめします。
病気休暇については、給与の100%が保障されますので、退職という重大な決断を一旦、保留した上で、しばらく休みをとることができます。
第118回『公務員(国家公務員、地方公務員)の方や民間企業にお勤めの方には休職代行(病気休暇取得代行)がおすすめな理由』について、をご参照ください。公務員の病気休暇について理解がすすめかと思います。
・関連コラム
第132回『公務員の退職代行の体験談と相談窓口(川越みずほ法律会計)』について
弁護士法人川越みずほ法律会計の紹介
いち早く退職代行を手掛け、今までも多数の相談及び解決事例があります。
今回、その中でもご質問が多いご相談事項をコラム形式でまとめました。
この記事の執筆者

弁護士清水 隆久
弁護士法人川越みずほ法律会計 代表弁護士
埼玉県川越市出身
城西大学付属川越高校卒業、中央大学法学部法律学科卒業、ベンチャー企業経営、労働保険事務組合の理事、社会保険労務士事務所の代表を経て、予備試験合格、司法試験合格、司法修習終了後、弁護士法人川越みずほ法律会計を設立、同弁護士法人代表に就任。労務・税務・法律・経営の観点から、企業法務に関わる傍ら、東から西へと全国を飛び回る。社会保険労務士時代に得た労働社会保険諸法令の細かな知識を活かし、かゆい所に手が届く退職代行サービスを目指して日々奮闘中。2019年に携わった労働事件(労働者側・使用者側の両方。労働審判を含む)は、60件以上となる。
TOPへ戻る